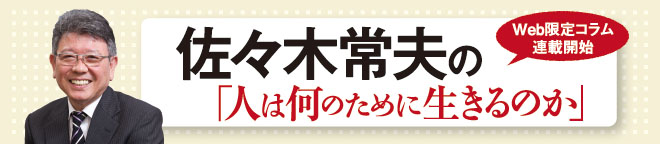第4回 渋沢栄一に学ぶ「好奇心」の力
自己成長を目指す読者のために、今月は「好奇心を忘れない」ことの重要性をお伝えしたい。
『自分が変わるための15の成長戦略』に、「なぜ? の数だけ人生はエキサイティングになる」という言葉がある。このフレーズを見て、私は渋沢栄一のことを思い出した。
近代日本の産業経済の礎を築いた渋沢栄一の伝記を読むと、「好奇心」ということに関して、彼の右に出る者はいないという思いに駆られる。
明治維新の直前、1867年フランス・パリの万国博覧会に徳川15代将軍慶喜(よしのぶ)の弟・清水昭武(あきたけ)が派遣されたとき、渋沢は、その対人能力を買われ、幕府の外国奉行と尊王攘夷の水戸藩で成る混成団のまとめ役として随行することになった。
パリに着くやいなや、彼の好奇心は全開する。アパートの賃貸契約について家主に根掘り聞いたり、店子さんに聞いたりする。下水道を見つけては、「どうしてこうなっているのか」とマンホールのフタを開けて、中に入り込んでしまう。日本から行った他の連中が昼寝している間に、朝から晩まで興味の赴くままに情報収集する。異常ともいえるほどの好奇心と行動力で、ヨーロッパの社会や文化を吸収していったのだ。
しかし、渋沢がパリにいる間に幕府は倒れ、新政府の命により、急遽帰国を余儀なくされてしまう。帰国後は、隠居していた主君・徳川慶喜の近くに住んでいたが、大蔵省のナンバー2であった大隈重信がパリでの渋沢の振る舞いを聞きつけ、「あんな面白い男を使わなければ損だ、あんなに好奇心の強い男はいないのだから」と、大蔵省の高官に取り立てる。その後、渋沢は地租改正や鉄道敷設などの大仕事を成すのだ。
とにかく人や物事にぶつかったら、渋沢は「なぜ? なぜ? なぜ?」と聞く。
明治維新後における日本の経済成長は、第一国立銀行(日本で最初の銀行)、日本郵船、キリンなど500以上の会社や銀行を興した渋沢から始まった。そして、その土台にあったのが「好奇心」なのである。
■好奇心は、自発的な学習の栄養剤
会社の中にも好奇心の強い人がいて、そういう人はだいたい仕事ができる。
マクスウェルも上記の本の中で次のようなことを書いているではないか。
「好奇心は自発的な学習の一番の栄養剤である。好奇心がある人は、言われなくてもあれこれ質問をし、探求する。いつでもどこでも自然とそうなるのだ。……好奇心は平凡なアイデアを膨らませ、可能性を広げてくれる。『なぜ』と考えることで、想像力に火がつく。新たな発見へとつながっていく。平凡の壁を乗り越え、非凡な生き方を可能にする」
最近ワクワクしたことを思い出せないといった人や、成長の速度を上げたいと願う人は、マクスウェルの「成長戦略」をひも解いてみてほしい。そこには、好奇心の芽をもっと大きく育てるためのヒントがある。
著者プロフィール
1944年秋田市生まれ。1969年東京大学経済学部卒業、同年東レ入社。自閉症の長男に続き、年子の次男、年子の長女が誕生。初めて課長に就任したとき、妻が肝臓病に罹患。うつ病も併発し、入退院を繰り返す(現在は完治)。
すべての育児・家事・看病をこなすために、毎日6時に退社する必要に迫られる。そこで、課長職の本質を追究して、「最短時間」で「最大の成果」を生み出すマネジメントを編み出す。2001年、東レで取締役就任。2003年より東レ経営研究所社長。経団連理事、政府の審議会委員、大阪大学客員教授を歴任。「ワーク・ライフ・バランス」のシンボル的存在となる。
著書に『ビッグツリー』『部下を定時に帰す仕事術』『そうか、君は課長になったのか。』『働く君に贈る25の言葉』など、ベストセラー多数。
バックナンバー
- 2013年09月02日 第1回 “それでもなお”が、自分を大きくする
- 2013年09月11日 第4回 渋沢栄一に学ぶ「好奇心」の力
- 2013年10月01日 第2回 人がもっとも成長する時とは
- 2013年11月06日 第5回 素早く、質の高い仕事を完成させるには
- 2013年11月07日 第3回「働く理由」は、金を稼ぐことだけではない
- 2014年01月08日 第6回 リーダーの条件とは何か