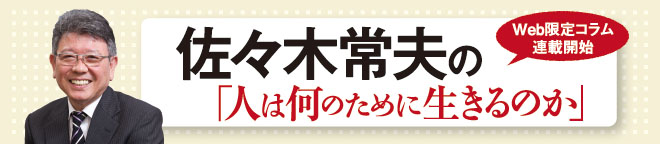第6回 リーダーの条件とは何か
私は経団連の理事を務めていたこともあり、多くのビジネスリーダーや経営者と面識がある。
しかし、彼らと話していて、上に立つ者としての「人格」という意味で、「いかがなものか」と感じることがある。だから、中には従業員に対して「死ぬほど働け」という言葉が出てくる人がいるのかもしれない。そういう人は経営者としては非常に優秀なのだろうが、それでは本当のリーダーとは言えないのではないかと思うのだ。一部上場の大会社の社長も何人も知っているが、本当のリーダー、人格者と言えるリーダーは数えるほどしかいないと感じる。
誰もが認める人格者であった経営者といえば、土光敏夫さんくらいではないか。土光さんは石川島播磨重工業や東芝の社長を歴任後、経団連会長や第二臨調会長として華々しい実績を残した人物でありながら、勤倹質素な暮らしぶりで「メザシの土光さん」として広く知られている。
土光さんの賞賛すべきところは、すべての行動が「自分のため」ではなく「世のため人のため」に端を発していることである。
組織においては、能力がそこそこあって、社内政治でうまく立ち回れば偉くなれる。つまり企業のトップには、人格者でなくても就くことができる。むしろ、人格などないほうが、なれる可能性が高いかもしれない。
また、本当のリーダーとは、ある時がきたら、後進に道を譲るものだ。地位に連綿とし、「70歳を超えてトップに復帰」「90代まで会社に来てトイレに行くにも介添え付き」などといった元トップたちのその後の話を聞くと、私などは腰を抜かす思いだ。これでは、「私にはリーダーシップがありません」と宣言しているのと同じだ。
政治の世界も似たり寄ったりで、「よくぞ、こんな人が首相になった」という例が山ほどある。「リーダー」ではなく、「首相」になっただけなのだ。
最近では世の中の組織の長に、リーダーシップを求めても無理なのかもしれないと、あきらめ半分だ。
■「人を動かす人」に必要な器とは
私のリーダーの定義とは、「その人と一緒に仕事をしていると勇気と希望をもらえる人」である。そういう人とは、会社の中であれば、課長にもいるし、新入社員にもいる。家庭の主婦にも、障害者にもいる。
たとえば、私が出席している審議会で、隣の席に座っているのは『五体不満足』を書いた乙武洋匡君だが、彼と話をしていると、私を含め多くの人が勇気と希望をもらえる。立派なリーダーである。
人格形成とは一朝一夕にできるものではない。マクスウェルは『自分が変わるための15の成長戦略』の中で、このようなことを書いている。
「品性を磨き、謙虚になるためには、『人のために尽くす』ことだ。相手のことをまず第一に考えることで、自己愛も客観性もちょうどいいところに落ち着く」
「正直さや誠実さを核とした優れた人格は、人生のいかなる局面においても成功に欠かせないものだ。優れた人格を欠く人間は、砂上の楼閣のように崩れ去る運命にある」
いかがだろうか。エゴを抑えて他人のために努力することはなかなか困難なことだろう。
この本の「監訳者まえがき」でも書いたとおり、特に若いうちは金銭欲や出世欲が、働くモチベーションとなる場合が多い。しかし、ある程度の経験を積んでいくうちに、「周囲の人があなたの働く動機を感じ取っていること」「利他の精神がなければ結果はついてこないこと」に気づくはずだ。
自分のために始めたことが、次第に世のため、人のためになる──私流の言い方をすれば、「欲が磨かれて、志になる」のである。
著者プロフィール
1944年秋田市生まれ。1969年東京大学経済学部卒業、同年東レ入社。自閉症の長男に続き、年子の次男、年子の長女が誕生。初めて課長に就任したとき、妻が肝臓病に罹患。うつ病も併発し、入退院を繰り返す(現在は完治)。
すべての育児・家事・看病をこなすために、毎日6時に退社する必要に迫られる。そこで、課長職の本質を追究して、「最短時間」で「最大の成果」を生み出すマネジメントを編み出す。2001年、東レで取締役就任。2003年より東レ経営研究所社長。経団連理事、政府の審議会委員、大阪大学客員教授を歴任。「ワーク・ライフ・バランス」のシンボル的存在となる。
著書に『ビッグツリー』『部下を定時に帰す仕事術』『そうか、君は課長になったのか。』『働く君に贈る25の言葉』など、ベストセラー多数。
バックナンバー
- 2013年09月02日 第1回 “それでもなお”が、自分を大きくする
- 2013年09月11日 第4回 渋沢栄一に学ぶ「好奇心」の力
- 2013年10月01日 第2回 人がもっとも成長する時とは
- 2013年11月06日 第5回 素早く、質の高い仕事を完成させるには
- 2013年11月07日 第3回「働く理由」は、金を稼ぐことだけではない
- 2014年01月08日 第6回 リーダーの条件とは何か