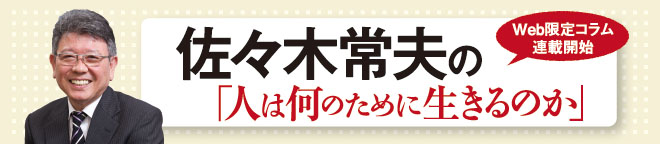第5回 素早く、質の高い仕事を完成させるには
私はいつも「プアなイノベーションより優れたイミテーション」と言っている。
会社の仕事は、大半が同じことの繰り返しで、誰かがどこかで似たようなことをしている。だから、自分の頭で一から考えるより、先人の知恵を借りるのが賢いやり方だ。効率にも、仕事の出来にも格段の差がつく。
『自分が変わるための15の成長戦略』の中に、私の考えと共通する戦略がある。それは、「手本を見つける」ということだ。
30代前半のとき、私は東レの取引会社の再建のために派遣されることとなった。大きな取引先であり、もし倒産ということになれば、負債総額が1600億円にもなる。そうなると、戦後2番目の規模の倒産ともなり、万が一の場合は数百社が連鎖倒産するという緊迫した状態だった。東レから12人のメンバーが派遣され、東レのメンツにかけても再建せよというプレッシャーの中、文字通り土日なく夜中まで働いた。そして3年半たった後、私は突然、東レに戻るよう内示を受け、東レの当時の売上の7割を占める繊維事業の中枢機能部署に配属された。ひととおりの業務引き継ぎを行なった後、最初に私がやったことが「書庫の整理」である。
「なんで書庫の整理なのか」と思うだろう。
そこには、昭和20年代から作成されてきた経営会議の資料が山ほどあった。私は作業着に着替えて、2週間以上朝から晩までその書庫に入り、すべての書類を読み、そのうち半分の不要なものを捨てた。
そして、残すべきもう半分の書類は、カテゴリー別に分類し、重要度のランキングをつけ、最後にファイルリストまでつくった。
この整理が終わった後、上司から何らかの仕事がくると、「それだったら、あのファイルとあのファイル」と3つほど取り出してきて、似たようなテーマを過去にどう分析し、結論付けたのか調べたのである。書庫にある考え方とフォーマット、着眼点をいただき、最新のデータに置き換えて、自分のアイデアを乗せる。
つまり、私のメンター(手本)とは、それまで東レの企画室に所属していた先輩たちだった、というわけだ。
■「下手な思いつき」より、「上手な模倣」
経営会議の資料は、途中で落第点がついた書類は一つもない。最後の最後、一番優れた作品が残っている。それを使って新しい仕事に活かすのだから、やることなすこと速くて、出来がいいに決まっている。
だから、私は部下にいつも、
「自分の頭を使うより先輩の作った優れた作品(書類)を盗みなさい、優れたイミテーションを繰り返しているうちに優れたイノベーションができるんだ」
と言ってきた。
これが、マクスウェルが言う「手本を見つけろ」ということなのだ。
最初は必ずしも生身の人間を手本にする必要はない。マクスウェルもデール・カーネギーの『人を動かす』や、ジェームズ・アレンの『「原因」と「結果」の法則』を〝最初の手本〟として、人とのつき合い方や自己実現の方法について学びを得ている。マクスウェルの言葉を借りれば、「本は、成長の出発点として申し分ないだけでなく、その後もずっと本から学ぶことは多い」のだ。今回私が監訳した、『自分が変わるための15の成長戦略』も成長を志す人の “メンター” となれば幸いである。
著者プロフィール
1944年秋田市生まれ。1969年東京大学経済学部卒業、同年東レ入社。自閉症の長男に続き、年子の次男、年子の長女が誕生。初めて課長に就任したとき、妻が肝臓病に罹患。うつ病も併発し、入退院を繰り返す(現在は完治)。
すべての育児・家事・看病をこなすために、毎日6時に退社する必要に迫られる。そこで、課長職の本質を追究して、「最短時間」で「最大の成果」を生み出すマネジメントを編み出す。2001年、東レで取締役就任。2003年より東レ経営研究所社長。経団連理事、政府の審議会委員、大阪大学客員教授を歴任。「ワーク・ライフ・バランス」のシンボル的存在となる。
著書に『ビッグツリー』『部下を定時に帰す仕事術』『そうか、君は課長になったのか。』『働く君に贈る25の言葉』など、ベストセラー多数。
バックナンバー
- 2013年09月02日 第1回 “それでもなお”が、自分を大きくする
- 2013年09月11日 第4回 渋沢栄一に学ぶ「好奇心」の力
- 2013年10月01日 第2回 人がもっとも成長する時とは
- 2013年11月06日 第5回 素早く、質の高い仕事を完成させるには
- 2013年11月07日 第3回「働く理由」は、金を稼ぐことだけではない
- 2014年01月08日 第6回 リーダーの条件とは何か