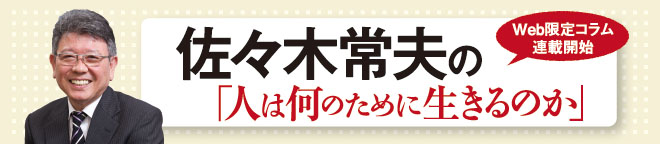第1回 “それでもなお”が、自分を大きくする
私は、「なぜ人間は生きるのか、働くのか」ということを自分なりに考えざるを得ない環境に育った。
これは、今は亡き母の教えによるところが大きい。母は19歳で結婚し、私たち男兄弟4人をもうけたが、27歳で未亡人になった。私がまだ6歳の時である。母は生計を立てるため、朝6時半には家を出て、夜は10時に帰ってくる生活。1年間で休むのは、たった3日くらい。そういう苦労をして、母は子どもを育て上げた。母は高校しか出ていなかったが、相当な努力家であり、前向きで、勉強家だった。私たち兄弟に「本を読め」と教えてくれたのも母だった。お金がないので、私立大学はダメだからと、兄弟みんなが国立の大学に進学したときの母の喜びようはなかった。母に苦労はかけたくないと、大学時代は仕送りなしを通した。
会社に入って結婚すると障害のある長男に続いて、年子で長男、長女が生まれた。私が課長になったのと同時に妻が肝硬変を患う。精神的にも参ってしまった妻は、その後うつ病を患い、彼女は入退院を43回も繰り返す。それ以外のことも含め、様々な困難があった。
■「自己実現欲求」のさらに上にあるものとは?
そういう環境の中で「人は何のために生きるのか」ということを必然的に深く考えさせられ、『論語』『夜と霧』『7つの習慣』をはじめ、人生論、自己啓発書の名著もたくさん読んできた。
なかでもアメリカの心理学者、アブラハム・マズローの提唱した「人間は生理的欲求からはじまり、安全欲求、所属と愛の欲求、承認の欲求、そして自己実現の欲求に向かって絶えず成長する」という「欲求段階説」を読んだときは「なるほど、人間は自己実現のために働いているのか」と深く感じ入った。しかしその後、「逆説の10カ条」という人生訓に出合ったときは、さらに深い感銘を受けた。
「逆説の10カ条」とは、アメリカ人のケント・M・キースが書いた処世訓で、マザー・テレサも感動したことで、世界的にも有名だ。以下に挙げてみたい。
【逆説の10カ条】ケント・M・キース
1.人は不合理で、わからず屋で、わがままな存在だ。
それでもなお、人を愛しなさい。
2.何か良いことをすれば、
隠された利己的な動機があるはずだと人に責められるだろう。
それでもなお、良いことをしなさい。
3.成功すれば、うその友だちと本物の敵を得ることになる。
それでもなお、成功しなさい。
4.今日の善行は明日になれば忘れられてしまうだろう。
それでもなお、良いことをしなさい。
5.正直で素直なあり方はあなたを無防備にするだろう。
それでもなお、正直で素直なあなたでいなさい。
6.最大の考えをもった最も大きな男女は、
最小の心をもった最も小さな男女によって撃ち落とされるかもしれない。
それでもなお、大きな考えを持ちなさい。
7.人は弱者をひいきにはするが、勝者の後にしかついていかない。
それでもなお、弱者のために戦いなさい。
8.何年もかけて築いたものが一夜にして崩れ去るかもしれない。
それでもなお、築きあげなさい。
9.人が本当に助けを必要としていても、
実際に助けの手を差し伸べると攻撃されるかもしれない。
それでもなお、人を助けなさい。
10. 世界のために最善を尽くしても、
その見返りにひどい仕打ちを受けるかもしれない。
それでもなお、世界のために最善を尽くしなさい。
この「逆説の10カ条」を知り、私はマズローの「自己実現欲求」には、もう一つ上があることを知った。それは、「自分を磨く」段階である。そして、「自分を磨く」とは、とりもなおさず「成長し続ける」というテーマにつながっていくことだと悟ったわけである。
このことは、このたび私の監訳した『自分が変わるための15の成長戦略』で、くわしく説き明かされている。その一節を今月のコラムの結びに変えさせていただきたい。
「神から人へのプレゼントは、潜在能力。人から神へのプレゼントは、それを伸ばすこと」
これは、今は亡き母の教えによるところが大きい。母は19歳で結婚し、私たち男兄弟4人をもうけたが、27歳で未亡人になった。私がまだ6歳の時である。母は生計を立てるため、朝6時半には家を出て、夜は10時に帰ってくる生活。1年間で休むのは、たった3日くらい。そういう苦労をして、母は子どもを育て上げた。母は高校しか出ていなかったが、相当な努力家であり、前向きで、勉強家だった。私たち兄弟に「本を読め」と教えてくれたのも母だった。お金がないので、私立大学はダメだからと、兄弟みんなが国立の大学に進学したときの母の喜びようはなかった。母に苦労はかけたくないと、大学時代は仕送りなしを通した。
会社に入って結婚すると障害のある長男に続いて、年子で長男、長女が生まれた。私が課長になったのと同時に妻が肝硬変を患う。精神的にも参ってしまった妻は、その後うつ病を患い、彼女は入退院を43回も繰り返す。それ以外のことも含め、様々な困難があった。
■「自己実現欲求」のさらに上にあるものとは?
そういう環境の中で「人は何のために生きるのか」ということを必然的に深く考えさせられ、『論語』『夜と霧』『7つの習慣』をはじめ、人生論、自己啓発書の名著もたくさん読んできた。
なかでもアメリカの心理学者、アブラハム・マズローの提唱した「人間は生理的欲求からはじまり、安全欲求、所属と愛の欲求、承認の欲求、そして自己実現の欲求に向かって絶えず成長する」という「欲求段階説」を読んだときは「なるほど、人間は自己実現のために働いているのか」と深く感じ入った。しかしその後、「逆説の10カ条」という人生訓に出合ったときは、さらに深い感銘を受けた。
「逆説の10カ条」とは、アメリカ人のケント・M・キースが書いた処世訓で、マザー・テレサも感動したことで、世界的にも有名だ。以下に挙げてみたい。
【逆説の10カ条】ケント・M・キース
1.人は不合理で、わからず屋で、わがままな存在だ。
それでもなお、人を愛しなさい。
2.何か良いことをすれば、
隠された利己的な動機があるはずだと人に責められるだろう。
それでもなお、良いことをしなさい。
3.成功すれば、うその友だちと本物の敵を得ることになる。
それでもなお、成功しなさい。
4.今日の善行は明日になれば忘れられてしまうだろう。
それでもなお、良いことをしなさい。
5.正直で素直なあり方はあなたを無防備にするだろう。
それでもなお、正直で素直なあなたでいなさい。
6.最大の考えをもった最も大きな男女は、
最小の心をもった最も小さな男女によって撃ち落とされるかもしれない。
それでもなお、大きな考えを持ちなさい。
7.人は弱者をひいきにはするが、勝者の後にしかついていかない。
それでもなお、弱者のために戦いなさい。
8.何年もかけて築いたものが一夜にして崩れ去るかもしれない。
それでもなお、築きあげなさい。
9.人が本当に助けを必要としていても、
実際に助けの手を差し伸べると攻撃されるかもしれない。
それでもなお、人を助けなさい。
10. 世界のために最善を尽くしても、
その見返りにひどい仕打ちを受けるかもしれない。
それでもなお、世界のために最善を尽くしなさい。
この「逆説の10カ条」を知り、私はマズローの「自己実現欲求」には、もう一つ上があることを知った。それは、「自分を磨く」段階である。そして、「自分を磨く」とは、とりもなおさず「成長し続ける」というテーマにつながっていくことだと悟ったわけである。
このことは、このたび私の監訳した『自分が変わるための15の成長戦略』で、くわしく説き明かされている。その一節を今月のコラムの結びに変えさせていただきたい。
「神から人へのプレゼントは、潜在能力。人から神へのプレゼントは、それを伸ばすこと」
著者プロフィール
佐々木常夫(ささきつねお)
1944年秋田市生まれ。1969年東京大学経済学部卒業、同年東レ入社。自閉症の長男に続き、年子の次男、年子の長女が誕生。初めて課長に就任したとき、妻が肝臓病に罹患。うつ病も併発し、入退院を繰り返す(現在は完治)。
すべての育児・家事・看病をこなすために、毎日6時に退社する必要に迫られる。そこで、課長職の本質を追究して、「最短時間」で「最大の成果」を生み出すマネジメントを編み出す。2001年、東レで取締役就任。2003年より東レ経営研究所社長。経団連理事、政府の審議会委員、大阪大学客員教授を歴任。「ワーク・ライフ・バランス」のシンボル的存在となる。
著書に『ビッグツリー』『部下を定時に帰す仕事術』『そうか、君は課長になったのか。』『働く君に贈る25の言葉』など、ベストセラー多数。
1944年秋田市生まれ。1969年東京大学経済学部卒業、同年東レ入社。自閉症の長男に続き、年子の次男、年子の長女が誕生。初めて課長に就任したとき、妻が肝臓病に罹患。うつ病も併発し、入退院を繰り返す(現在は完治)。
すべての育児・家事・看病をこなすために、毎日6時に退社する必要に迫られる。そこで、課長職の本質を追究して、「最短時間」で「最大の成果」を生み出すマネジメントを編み出す。2001年、東レで取締役就任。2003年より東レ経営研究所社長。経団連理事、政府の審議会委員、大阪大学客員教授を歴任。「ワーク・ライフ・バランス」のシンボル的存在となる。
著書に『ビッグツリー』『部下を定時に帰す仕事術』『そうか、君は課長になったのか。』『働く君に贈る25の言葉』など、ベストセラー多数。
バックナンバー
- 2013年09月02日 第1回 “それでもなお”が、自分を大きくする
- 2013年09月11日 第4回 渋沢栄一に学ぶ「好奇心」の力
- 2013年10月01日 第2回 人がもっとも成長する時とは
- 2013年11月06日 第5回 素早く、質の高い仕事を完成させるには
- 2013年11月07日 第3回「働く理由」は、金を稼ぐことだけではない
- 2014年01月08日 第6回 リーダーの条件とは何か