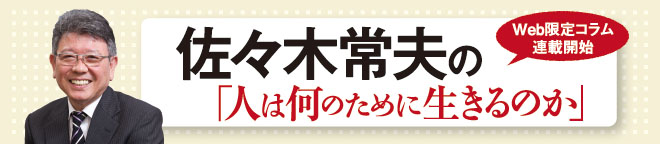第2回 人がもっとも成長する時とは
今月は、「人がもっとも成長する時」について考えてみたい。
私が自分のサラリーマン時代を通じて一番成長した時期というのは、四十代だったと思っている。二十代から三十代は「成長角度」が高いが、経験も知識もないから、回り道やミスも多い。ところが、経験を積んでいくと、余計なこと、下手なことはしなくなる。 そして、四十代になると部下を持つようになるが、この経験によって俯瞰で物事を見られるようになり、洞察力も磨かれる。自分だけでなくチーム全体のことを考える習慣によって、人間的にも深みが増してくるようになる。
成長し続ける自分でいるために、私は「四十代は、しなやかに生きなさい」と言っている。なるべく部下に仕事をまかせて、自分は早く帰宅し、先月のコラム(コラム第一回にリンクを飛ばす)で紹介した本を読むなど、自己啓発の勉強をするのだ。
興味深いことだが、「自尊心」と、仕事などの「成果」は比例している。仕事上の知識・スキルを深め、磨くことは職業人であれば当然だが、心の持ち方、人格を陶冶することで、それまでとは違ったレベルでの成長を実感でき、成果も自然とついてくるようになる。
もちろん、自分の成長だけではなく、部下を持つ人は彼らの成長にも気を配らねばならない。私はこれまで多くの部下、仲間を見てきて、会社の中で「モチベーション高く仕事ができるとき」とは、「仕事を通じて、自分の成長を実感できるとき」だと思っている。 だから、私は部下との面談の際には、「今、あなたはこの水準にいて、去年はここまでだった。だから、今年一年でこれだけ成長したんだ」と、部下の立ち位置を示すことを心がけてきた。
「今、ここにいる。次は、ここまで目指そう」──そう実感したとき、私たちは頑張れる。
そして、頑張る気持ちを下支えしてくれるのが「自尊心」だろう。自尊心や自己評価が低ければ、頑張ろうという意欲も続かない。だからこそ、自己啓発、つまり心や人格を磨くことの重要性を強調しすぎることはないのだ。
■「逆境」を糧にできる人、できない人
さて、『自分が変わるための15の成長戦略』で、著者のマクスウェルは「人は立ち止まったときに、自分の立ち位置を理解し、成長する」と書いている。
就職・異動・転職したとき、新しいプロジェクトに挑戦するとき、そして、左遷や失敗など「逆境」にあるとき──人は立ち止まり、これまでの自分を振り返り、将来について考える。
「経験は最高の教師」と言うが、立ち止まって内省することで、「経験」が「見識」に代わり、より深みのある人生を生きていくことができる。
つらい経験から立ち直り、成長した自分に出会える人と、いつまでも拘泥して抜け出せない人の違いは、「問題にどう立ち向かうか」その心構えの違いにある。
転機や逆境を「貴重な経験」として敢然と引き受ける人は、どんな状況にあっても力強く生きていけるだろう。
私自身、仕事、家族の問題で、多くの「逆境」を経験してきた。そのたびに、その運命を受け入れてきたつもりだが、東レの取締役を志半ばで退いたときは「仕方がないな」と思う反面、「東レに忘れ物をしてきた」という気持ちも強くあった。
そして、この気持ちがきっかけとなり、働きながら家族再生を果たした自伝的な本『ビッグツリー』を書いた。家族の絆、仕事とは何か、人生とは何かについて私が綴ったその本には、自分でも驚くほどの反響があった。その後、『部下を定時に帰す仕事術』を書くと、それがまた話題になって、予想以上に多くのビジネスマンに読んでもらえることになった。
人生とは、本当にわからないものである。
本を出すことで、それまでとは全く違った新しい世界が広がった。家族の絆は、いっそう強くなった。そのいずれも、退任した当時は思いもしなかったことだ。
逆境を逆境にするのは、自分である。
運命を受け入れ、立ち向かい、ある時は発奮材料にする──そのような姿勢が「逆境をものともしない自分」「成長し続ける自分」をつくるのではないだろうか。
私が自分のサラリーマン時代を通じて一番成長した時期というのは、四十代だったと思っている。二十代から三十代は「成長角度」が高いが、経験も知識もないから、回り道やミスも多い。ところが、経験を積んでいくと、余計なこと、下手なことはしなくなる。 そして、四十代になると部下を持つようになるが、この経験によって俯瞰で物事を見られるようになり、洞察力も磨かれる。自分だけでなくチーム全体のことを考える習慣によって、人間的にも深みが増してくるようになる。
成長し続ける自分でいるために、私は「四十代は、しなやかに生きなさい」と言っている。なるべく部下に仕事をまかせて、自分は早く帰宅し、先月のコラム(コラム第一回にリンクを飛ばす)で紹介した本を読むなど、自己啓発の勉強をするのだ。
興味深いことだが、「自尊心」と、仕事などの「成果」は比例している。仕事上の知識・スキルを深め、磨くことは職業人であれば当然だが、心の持ち方、人格を陶冶することで、それまでとは違ったレベルでの成長を実感でき、成果も自然とついてくるようになる。
もちろん、自分の成長だけではなく、部下を持つ人は彼らの成長にも気を配らねばならない。私はこれまで多くの部下、仲間を見てきて、会社の中で「モチベーション高く仕事ができるとき」とは、「仕事を通じて、自分の成長を実感できるとき」だと思っている。 だから、私は部下との面談の際には、「今、あなたはこの水準にいて、去年はここまでだった。だから、今年一年でこれだけ成長したんだ」と、部下の立ち位置を示すことを心がけてきた。
「今、ここにいる。次は、ここまで目指そう」──そう実感したとき、私たちは頑張れる。
そして、頑張る気持ちを下支えしてくれるのが「自尊心」だろう。自尊心や自己評価が低ければ、頑張ろうという意欲も続かない。だからこそ、自己啓発、つまり心や人格を磨くことの重要性を強調しすぎることはないのだ。
■「逆境」を糧にできる人、できない人
さて、『自分が変わるための15の成長戦略』で、著者のマクスウェルは「人は立ち止まったときに、自分の立ち位置を理解し、成長する」と書いている。
就職・異動・転職したとき、新しいプロジェクトに挑戦するとき、そして、左遷や失敗など「逆境」にあるとき──人は立ち止まり、これまでの自分を振り返り、将来について考える。
「経験は最高の教師」と言うが、立ち止まって内省することで、「経験」が「見識」に代わり、より深みのある人生を生きていくことができる。
つらい経験から立ち直り、成長した自分に出会える人と、いつまでも拘泥して抜け出せない人の違いは、「問題にどう立ち向かうか」その心構えの違いにある。
転機や逆境を「貴重な経験」として敢然と引き受ける人は、どんな状況にあっても力強く生きていけるだろう。
私自身、仕事、家族の問題で、多くの「逆境」を経験してきた。そのたびに、その運命を受け入れてきたつもりだが、東レの取締役を志半ばで退いたときは「仕方がないな」と思う反面、「東レに忘れ物をしてきた」という気持ちも強くあった。
そして、この気持ちがきっかけとなり、働きながら家族再生を果たした自伝的な本『ビッグツリー』を書いた。家族の絆、仕事とは何か、人生とは何かについて私が綴ったその本には、自分でも驚くほどの反響があった。その後、『部下を定時に帰す仕事術』を書くと、それがまた話題になって、予想以上に多くのビジネスマンに読んでもらえることになった。
人生とは、本当にわからないものである。
本を出すことで、それまでとは全く違った新しい世界が広がった。家族の絆は、いっそう強くなった。そのいずれも、退任した当時は思いもしなかったことだ。
逆境を逆境にするのは、自分である。
運命を受け入れ、立ち向かい、ある時は発奮材料にする──そのような姿勢が「逆境をものともしない自分」「成長し続ける自分」をつくるのではないだろうか。
著者プロフィール
佐々木常夫(ささきつねお)
1944年秋田市生まれ。1969年東京大学経済学部卒業、同年東レ入社。自閉症の長男に続き、年子の次男、年子の長女が誕生。初めて課長に就任したとき、妻が肝臓病に罹患。うつ病も併発し、入退院を繰り返す(現在は完治)。
すべての育児・家事・看病をこなすために、毎日6時に退社する必要に迫られる。そこで、課長職の本質を追究して、「最短時間」で「最大の成果」を生み出すマネジメントを編み出す。2001年、東レで取締役就任。2003年より東レ経営研究所社長。経団連理事、政府の審議会委員、大阪大学客員教授を歴任。「ワーク・ライフ・バランス」のシンボル的存在となる。
著書に『ビッグツリー』『部下を定時に帰す仕事術』『そうか、君は課長になったのか。』『働く君に贈る25の言葉』など、ベストセラー多数。
1944年秋田市生まれ。1969年東京大学経済学部卒業、同年東レ入社。自閉症の長男に続き、年子の次男、年子の長女が誕生。初めて課長に就任したとき、妻が肝臓病に罹患。うつ病も併発し、入退院を繰り返す(現在は完治)。
すべての育児・家事・看病をこなすために、毎日6時に退社する必要に迫られる。そこで、課長職の本質を追究して、「最短時間」で「最大の成果」を生み出すマネジメントを編み出す。2001年、東レで取締役就任。2003年より東レ経営研究所社長。経団連理事、政府の審議会委員、大阪大学客員教授を歴任。「ワーク・ライフ・バランス」のシンボル的存在となる。
著書に『ビッグツリー』『部下を定時に帰す仕事術』『そうか、君は課長になったのか。』『働く君に贈る25の言葉』など、ベストセラー多数。
バックナンバー
- 2013年09月02日 第1回 “それでもなお”が、自分を大きくする
- 2013年09月11日 第4回 渋沢栄一に学ぶ「好奇心」の力
- 2013年10月01日 第2回 人がもっとも成長する時とは
- 2013年11月06日 第5回 素早く、質の高い仕事を完成させるには
- 2013年11月07日 第3回「働く理由」は、金を稼ぐことだけではない
- 2014年01月08日 第6回 リーダーの条件とは何か